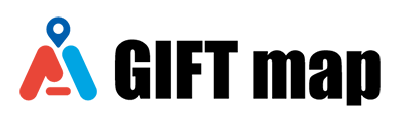- ホーム
- ビジネスマッチングコラム 一覧
- ビジネスマッチングコラム vol.54
ビジネスマッチングコラム vol.54


EBITDAの基本的な定義と意味
EBITDA(Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization)は、会社の収益力を評価する指標として広く活用されています。EBITDAを直訳すると、下記のとおりです。
Earnings …… 収益、利益
Before …… 前
Interest …… 金利、利子、利息
Taxes …… 税金
Depreciation …… 有形固定資産の減価償却費
Amortization …… 無形固定資産の減価償却費
読み方は、イービットディーエー、イービットダー、イービッタなど、さまざまです。計算式はいくつかありますが、
一般的には、EBITDA=営業利益+減価償却費で表されます。営業利益や経常利益と並ぶ企業評価指標のひとつです。
営業利益は、本業の売上高から売上原価と販売費や従業員の給与、広告宣伝費、交際費などの経費を引いた利益です。
本業以外で稼いだ利益や損失(たとえば、不動産の賃貸収入や投資活動による利益や損失)は含まれないので、営業利益は本業で稼いだ利益です。減価償却費は、設備や建物などの有形固定資産や、特許権、商標権などの無形固定資産の価値が、時間とともに減少することを反映した会計上の費用です。これは実際のキャッシュアウトをともないません。営業利益は実際のキャッシュアウトをともなわない減価償却費を経費としているため、EBITDAでは減価償却費を足し戻すことで、よりキャッシュフローに近い実質的な利益を算出することができます。つまり、EBITDAは会社の本業からキャッシュを生み出す力をより直接的に計れるのです。そのため会社の収益力をキャッシュベースで見るための指標として使われ、経営の実態を把握しやすくなります。
M&AにおいてEBITDAが重視される理由
非上場会社の中小企業のM&Aにおいては、売手会社の企業価値を評価する場面でEBITDAが重要視され用いられます。上記で記したように、質が高く現金の裏付けのある利益がわかるためです。
EBITDAは、会計処理の影響を排除しています。例えば、会社が多額の借入をしていた場合、支払利息が大きく利益が低くなる可能性がありますが、資金調達をした利息は調達先により異なります。預金や社債、貸付金などの利息や銀行借り入れなどによる利息は、会社の稼ぐ力に直接的には影響がありません。そのため、EBITDAでは、財務活動による収益、経費は除外します。
また、EBITDAは、異なる会計基準を持つ会社間の比較を容易にします。減価償却や税制は国や業界ごとに異なるため、利益だけでは会社間の収益性を比較することが難しいのです。しかし、EBITDAを活用することで、異なる国や業界の会社でも収益力を比較しやすくなります。EBITDAは国内だけではなく国際的に広く使われています。
したがってM&Aを行う際に、売手会社の実力を公平に評価することができます。
M&A後に削減できるコスト
M&Aにおいては、EBITDAの考え方を拡大し、減価償却費だけではなく、M&A後に不要となるコストも利益とする場合もあります。買手が買収したあとの事業の収益性を知るために、M&A後に必要のないコストは省きます。
たとえば、M&A後に役員が退任するのであれば、役員報酬を控除します。M&A後に以前の取引先との関係の保ち方が変わる場合は交際費が不要になるかもしれません。ほかにも、社用車の整理を行うことで不要となる車両の維持費の削減やブランド統合による広告・宣伝費の削減、物流拠点の整理ができ不要になった倉庫などの賃料や配送コストの削減が考えらえるほか、システム統合により旧システムが不要になり、それにともなうコストを抑えることもできるかもしれません。M&A後の財務戦略の見直しにより、有利な条件での借換えや不要な借入の整理ができます。このようにM&A後に不要となるコストも利益とします。それぞれのM&Aにより、不要となるコストは異なりますので、コストを一つひとつ丁寧に見て差し引くことで、M&A後のより現実に近い、収益力を知ることができます。
返済・投資体力を見極める
M&Aにおいて買手が売手会社を評価する際、M&A後に売手会社が安定的にキャッシュを生み出し、負債を無理なく返済できるかという視点は重要です。EBITDAは本業によって生み出すキャッシュの力をダイレクトに把握できる指標であるため、ネットキャッシュ(返済能力)の評価に役立ちます。たとえば、「EBITDAが1億円あるので、年5,000万円の借入返済は余裕がある」と考えることができます。「EBITDAが高い=お金に余裕がある」と考えると新しい設備への投資や事業の拡大もしやすくなり、投資余力の評価にも役立ちます。
M&Aにおける“利益圧縮”の実態
中小企業のM&Aにおいて、売手社長が譲渡前に経費の払い出しを行うケースは少なくありません。これは、節税目的で意図的に利益を圧縮し、税負担を軽減するための施策です。たとえば、役員報酬の引き上げ、交際費や福利厚生費の先払い、棚卸資産の評価引き下げなどが該当します。しかし、買手にとって重要なのは、その会社が本来どれだけの収益力を持っているのかを見極めることです。特にオーナー経営者による私的な費用支出が多い場合、EBITDAの考え方を活用することで、その背後にある正味の利益構造が浮かび上がってきます。
売手としては、利益を意図的に圧縮して税効果を得つつも、買手側には正常収益力を正確に示す工夫が求められます。買手は、帳簿上の利益だけにとらわれずEBITDAなど正味のもうけを理解して企業価値を正しく見極める目が必要となるのです。
EBITDAのデメリットと留意点
上記では、減価償却費や不要となるコストを考慮しないことのメリットを記載しましたが、減価償却費や不要コストの影響を考慮しないデメリットもあります。減価償却を除外しているため、過剰な設備投資などを正確に捉えることができません。EBITDAはキャッシュに着目した収益性をはかりますが、実際のキャッシュフローとは異なります。また、負債や資金調達コストを考慮しないデメリットもあります。借入金が多い会社でもEBITDAが高いと健全に見えてしまいます。
異なる国や業界の会社同士の比較がしやすいと記載しましたが、業種によって設備投資の規模や利益の構造が大きく異なるため、単純な数値比較だけでは実態を見誤る可能性があります。たとえば、設備投資が多い業種では減価償却費を除いたEBITDAが実態以上に良く見えることや、先行投資が大きい業種は実態よりも良くないように見えることがあります。数字の背景にある意味合いを読み解き、EBITDAを加減し調整する必要があります。
さいごに
EBITDAは、会計上の利益とは異なり、営業利益に減価償却費や経費を足し戻すことで、会計処理や資本構成、税率といった要因の影響を除き、企業の“キャッシュ創出能力”や“事業の本質的な収益性”を評価する指標として有効になります。活用される際は、EBITDAの特徴と注意点をよく理解したうえで、状況に応じて活用ください。M&Aの際は、EBITDAだけを評価指標として活用するのではなく、フリーキャッシュフローやそのほかの指標も参考にし、売手会社の価値を見極めることが大切です。
M&Aをご検討されている方は、まずは<support@gift-map.jp>宛に相談してみませんか。
2025.8.22掲載