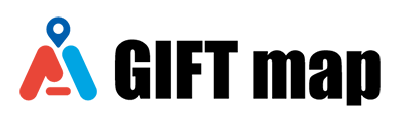- ホーム
- ビジネスマッチングコラム 一覧
- ビジネスマッチングコラム vol.55
ビジネスマッチングコラム vol.55


のれんの奥に宿る価値
街角の老舗の前を通ると、風に揺れる布が目に入る。そこには店名が染め抜かれ、長年の歴史と誇りが静かに漂っている。その先には、気さくな店主がいて、常連の笑い声が響く。
暖簾(のれん)は、単なる布でつくられた広告ではありません。店の信用、店主の覚悟、そして客との関係性を象徴する「目に見える信頼」です。この「暖簾」が持つ意味合いが、やがて企業の世界にも受け継がれ、会計の場面で「のれん」として表現されるようになりました。会社が築いてきた目に見えない価値、売上や利益では測れない、会社が時間をかけて築き上げた信用力、ブランド、顧客とのつながり。こうした目に見えない資産が、「のれん」です。つまり「のれん」は、数字では語りきれない会社の歴史や物語を映し出すものなのです。
帳簿に載らない資産
会社は製品やサービスを提供するだけではなく、時間をかけて信頼やブランドを育てています。たとえば、顧客が「この会社なら安心」と思う理由は、価格や性能だけではありません。対応の早さや丁寧さ、社員の専門性、納期遵守や品質管理の徹底、顧客からの口コミなど、こうした要素が会社の信用をつくります。このような価値は、会計上「自己創設のれん」と呼びます。ところが、自己創設のれんは財務諸表には現れません。というのも、客観的な評価が難しく数値化する基準が存在しないため、恣意的な資産計上を防ぐ必要があるのです。会社が持つ「見えない資産」は、会計上は簿外資産となります。会社が長年の努力で築いた信用力やブランド価値は、会計上ではないがしろにされているといえます。ところが、自己創設のれんは会社の収益力にかなりのインパクトを与えます。たとえば、同じ商品を販売していても、信頼されている会社の方がより多くあるいは高値で売れることがあります。これは、のれんが価格決定力を持っていることを示しています。損益計算書には高い売上や利益としてぼんやりとは現れますが、貸借対照表には資産として原則記載されません。このような会社は見た目以上に強い経営力を持っており、表面的な財務諸表では読み解けない本質的な価値を秘めています。それが自己創設のれんの特徴です。収益力の高い会社は「正ののれん」、低い会社は「負ののれん」を持つとも考えられます。
のれんに目を向けることは、企業の本質に迫ることなのです。
のれんはすべての会社が持つ
「のれん」は特殊な会社だけにあるものではありません。事業を継続してきたすべての会社が、「のれん」を持っています。たとえ貸借対照表に記載されていなくても、長年積み上げてきた信用力、顧客関係、技術力などは無形の資産として企業価値を形成しています。
M&Aで可視化される「のれん」
のれんが数値化され、財務諸表に登場する場合があります。それはM&A(企業買収)のときです。なぜなら、M&Aは、目に見える資産だけでなく、売手会社が築いてきた信用力やブランド価値、顧客関係、人財、ノウハウ、売手会社に対して期待する将来の収益力を買うからです。つまり、買収価格には「稼ぐ力」への期待が含まれており、その上乗せ分が「のれん」として認識されます。買収価格と帳簿上の純資産との差額が、買手会社の貸借対照表に「のれん」として計上されます。
株式譲渡によるM&Aの場合、「のれん」は買手会社の連結財務諸表にのみ計上されます。これは、売手会社が連結の範囲に含まれることで、買収価格と売手会社の純資産との差額が「のれん」として認識されるためです。一方、買手会社の個別財務諸表では、取得した株式は「投資その他の資産」として扱われ、「のれん」は計上されません。
事業譲渡によるM&Aの場合は、取得した資産や負債が買手会社の個別財務諸表に直接計上されます。買収価格が純資産を上回る部分は「営業権」として無形固定資産に計上されます。営業権は、会計上は「のれん」とは別科目として扱われますが、事業譲渡における「のれん」に相当する価値を表しており、実質的には同様の意味を持ちます。
また、株式譲渡によるM&Aの場合、売手会社が簿価で5億円の純資産を持ち、その売手会社が築いたブランドや顧客との関係、技術力などが高く評価されれば、買手会社が10億円を支払った場合の差額5億円が「のれん」という無形資産として買手会社の連結財務諸表に計上されます。買収価格が帳簿純資産を下回る場合には「負ののれん」が発生し、その差額は利益として処理されます。正ののれんは将来にわたって利益を生み出す源泉として資産に計上されますが、負ののれんは特別利益として買収年度の損益計算書に反映されます。特別”利益”として処理するのは、売手会社の純資産より低く買ったため、割安で資産を取得した、とみなされるためです。
のれんの金額は、売手会社の将来の収益力をどう評価するかによって決まるため、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法や年買法など、将来キャッシュフローや利益を基にした手法が使われます。M&Aは単なる資産の売買ではなく、いわゆる将来の収益力への期待に基づく売買であり、のれんはその見えない価値を映す存在なのです。
日本の会計基準と国際基準との違い
国際会計基準(IFRS)では、のれんは償却されません。代わりに、毎期「減損テスト」を行い、のれんの価値が下がったと判断された場合にのみ損失を計上します。のれんの価値が時間ではなく、事業の成果によって変動すると考えています。この違いは、企業の財務戦略に大きな影響を与えます。国際会計基準を採用する会社は、M&A後も利益を維持しやすく、成長性を示しやすいと言えます。一方、日本基準では、償却によって利益が削られるため、同じM&A戦略でも見劣りする可能性があります。日本の会計基準は保守的で、国際会計基準は将来の収益力を重視しています。どちらの基準も長所と短所があり、会社の成長戦略や財務方針、国際展開の有無によって、どちらの基準が適しているかは異なってきます。日本基準では安定的に費用を計上できる反面、償却が過剰になる可能性があり、国際会計基準ではのれんを「生きた資産」と捉え、真に価値が失われたと判断されたときのみ損失を計上するため、利益の変動リスクが高くなります。
のれん償却が成長戦略に及ぼす影響
日本の会計基準では、のれんは無形固定資産として貸借対照表に計上されますが、永続的な価値は認められていません。M&Aによって発生したのれんは「費用性資産」として扱われ、原則として最大20年以内に定額償却することが求められています。のれんの価値は、時代の流れや環境変化により時間とともに減少するという考えに基づいているためです。たとえば、純資産1億円の企業を5億円で買収した場合、のれんは4億円。これを8年で償却すると、年間5,000万円の費用が発生します。このとき営業利益が4,000万円しかなければ、実質的に利益はなくなり、赤字になる可能性があります。M&Aによる成長戦略が帳簿上の赤字に変わってしまうのです。したがってこの償却費はキャッシュアウトを伴わないにもかかわらず、販管費として損益計算書に計上されるため、営業利益や経常利益が継続的に圧迫され、会社の成長性が過小評価される可能性があります。
のれんを活かす買収戦略
M&Aで会社を買うときは、のれんをどう活かすかが収益化の鍵になります。たとえば、地方で高い認知度を持つ会社を買う場合、既存の店舗名や看板を残すことで、地域顧客の安心感を維持できます。また、業界特有のノウハウを持つ社員がいる企業なら、M&A後は業務フローやオペレーションを変えず、現場主導で改善提案を受ける方が収益につながります。
企業の未来を映すのれんの力
のれんは、過去の実績だけでなく、現在から未来への期待でもあります。つまり単なる会計項目ではなく、会社が築いてきた努力の結晶であり、これから何を実現するかというポテンシャル(可能性)の表れでもあります。だからこそ、M&Aの会社買収の判断においても、そののれんをどう活かすかが成否を分けるため、のれんの本質を見極め、未来に向けて活かすことができれば、企業はより力強く、持続的な成長と信頼を築いていけるでしょう。
自社ののれんについて知りたい方、M&Aをご検討されている方は、まずは<support@gift-map.jp>宛に相談してみませんか。
2025.9.26掲載